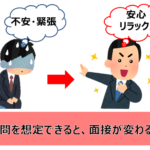目次
障害当事者であり、採用担当でもあるむじなです。
2017年12月22日に開催された厚生労働省の「労働政策審議会 (障害者雇用分科会)」において、精神障害者の雇用を促す特例措置を2018年4月から設けることが決まりました。
2018年には精神障害者の雇用が義務化されますので、精神障害者を雇用しやすくする意図があるのでしょう。
この特例措置は、企業にとっても、就職・転職を希望する精神障害者にとってもメリットのある話です。
この10年で4.9倍にまで増加した精神障害者の就職者数がさらに増加するでしょう。
今回は、この特例措置の内容と、企業・精神障害者の両者に与える影響についてお伝えします。
(データ出典:第74回 労働政策審議会障害者雇用分科会)
精神障害者雇用を促す特例措置とは
企業には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。現状では全従業員のうち2.0%(以上)となっていますが、2018年には法定障害者雇用率は2.2%に引き上げられます。
この「障害者雇用率」を計算する際のカウント方式が変更となるのが、今回の特例措置です。
障害者雇用率の算定基準では、週30時間以上(以下「フルタイム」)働いている障害者を1人、週20時間以上30時間未満(以下「短時間勤務」)で働く障害者を0.5人とカウントされます。
年々上昇する障害者雇用率に頭を悩ませている企業としては、せっかく障害者を雇うなら、0.5人としてカウントされる短時間勤務ではなく、フルタイムで雇いたいわけです。
そんな短時間勤務の障害者について、「雇用して(または手帳を取得して)3年以内の精神障害者」に限り「1人としてカウントできる」というのが、今回の特例措置の内容です。
この特例措置は5年間の時限措置のようなので、2018年4月から2023年3月まで有効ということですね。
それでは、以下この特例措置によって企業・精神障害者にどんなメリットがあるのか、解説します。
メリットその1:就労後の定着率向上が期待できる
精神障害者の雇用を促進するにあたり、大きな壁となっているのが、職場定着率の低さです。
就職1年後の職場定着率(辞めずに働いている割合)を見ると、身体障害者60.8%、知的障害者68.0%に対して、精神障害者は49.3%と、就職1年後には半分以上が辞めているのです。
精神障害者の1年後定着率を、さらに週の労働時間別でみると、「40時間以上」で42.4%、「30時間以上40時間未満」で50.5%、「20時間以上30時間未満」で60.4%と、労働時間が短いほど定着率が高いのです。
精神障害者の短時間就労を促進することは、職場の定着率を向上させるという大きなメリットがあるのです。
メリットその2:精神障害者の求人が増加する、採用のハードルが下がる
短時間勤務の雇用でも1人としてカウントされるとすれば、企業にとっては障害者雇用のハードルが下がります。
短時間勤務の雇用であれば、企業にとっての金銭的な負担も軽く済みますし、雇用率のために無理に「フルタイムで働ける障害者」に限って雇う必要がなくなるためです。
つまり、これまで精神障害者の求人を出していなかった企業を含め、精神障害者への求人数は確実に増加するでしょう。
そして、「まずは短時間勤務からじっくり慣れてくれればいい」というスタンスを取れるため、採用のハードルも下がるはずです。
「今は短時間勤務でしか働けない」「短時間勤務でもいいから働きたい」という精神障害者にとっては、大きなメリットになります。
問題になりそうなこと:短時間勤務からフルタイムになれるか
問題となりそうなのは、短時間勤務から就労を始めた精神障害者が、はたしてどれだけフルタイムに移行できるかということです。
働き始めのうちは、職場に慣れるため、仕事や生活のリズムを作るために短時間勤務から始めるのは良い選択だと思いますが、収入面を考えると、ずっと短時間勤務という訳にはいかないでしょう。
しかし、短時間勤務で働き始めた精神障害者のうち、フルタイムになれるのは25.2%というデータがあります。短時間勤務からフルタイムになれるのは4人に1人ということですね。
今回の特例措置により増える求人は、「フルタイムへの移行を前提とした短時間勤務」だと思いますので、25.2%という数字は当てはまらないかもしれませんが……どうなるかはわかりません。
まとめ:精神障害者の就職・転職はチャンス到来!
いずれにしろ、精神障害者の求人が増えて、採用のハードルも下がることは間違いないと思います。
しかし、精神障害者の求人が増えている一つの要因は、「精神障害者自体の数が増加しているから」です。
求人が増えて、採用のハードルが下がったとしても、「競争率」だけでみると今後そこまで下がってくることはないでしょう。
また、「きちんと障害者を評価してくれる(能力があればフルタイムになれる)企業」を見つけることも大切です。
応募者が集められる情報はごく限られますので、「より良い企業に就職・転職したい」「有利に就職・転職活動を進めたい」のであれば、転職エージェントを利用するのがおすすめです。
というよりも、使わないと損ですし、転職エージェントを利用しているライバルから一歩遅れることになります。
転職エージェントの利用はすべて無料なので、登録して話を聞いてみるだけでもよいでしょう。
合わせて読みたい